動力車免許について
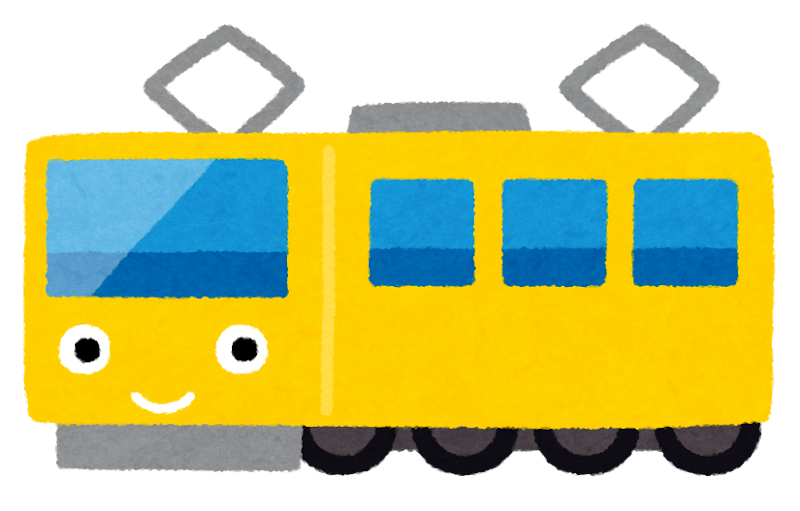
電車の運転免許である動力車操縦者免許について調べてこのブログに流れ着く方がかなり増えてきた様なので、現職電気車運転士としてアドバイスしてみようと思います。
私が甲種電気車動力車運転免許を取得したのは2000年の始め。
正直、今ほどユルユルな時代ではなかった。
養成所の入所試験の為の勉強は3か月間仕事の合間や帰宅後もみっちりやりました。
この時に、脳波・クレペリン・視力・張力などの医学適性も行った。
入所後は地獄の10か月でした。
勉強だけではなく、声の出し方・身なり・精神論。
100m離れた教員に向かって怒鳴るのではなく、大きな声で聞こえるようにスピーチを行う。
数10キロのマラソンなども行う。
教科書やPC教材を使い、運心・車両・保線・信号などの教育を受けつつ法的な使命、職責など叩き込まれる。
綱領・一般準則は一期一句点から丸まで完全に覚える。
覚えられなければ罵声を浴びされる。
中間試験に本試験とすべて学科をパスできれば良いが、一定数赤点を取るものは居る。
一人でも赤点を取ると全体責任となる会社でしたので、皆で皆を教えるという方式を取らざるおえなかった。
寝る間を惜しんで眠気を取り除く薬を飲みドリンク剤を服用しながらとにかく勉強した。
学科試験をパスした。
4月から実地訓練となる。
初日から新社会人や新学生がたくさん乗る電車で始まる。
2往復くらいは指導の横に乗り信号喚呼をしているが、橋梁名や道路名、踏切名や信号番号、カーブの半径など全部記憶していく。
初めての運転の時は指導の手添えでハンドルを動かしているので難しい事は考えていないが、手添え無しになった頃にはこの橋の名前は!?このカーブはRいくつ!?と質問の嵐。
もうパニックですよ
でもパニック起こしても電車は100km/hとかで進んでいく
もう自分の引っぱたいてでも覚えていくしかない。
慣れてくると指導と良好な関係を保っているグループと劣悪な関係のグループと明確に分かれていく。
私は初期こそ良好な関係でしたが、後半はお互いにいつ殺してやろうか!!と思う関係でした(笑
ハンドル試験の日は初電から駅に列車を見に行き、試験列車は何かを把握する。
今までやって覚えてきた車両の特性を再確認する。
そして試験に向かう。
難しい事書いてますが、とにかく精神論なのです。
ナヨナヨしている人は考え方変えて臨むか、そもそも電車の運転士になんかならない方がいい。
免許を取れたとしてもそういう子は事故や故障が起きた時は泣きを見ます。
コミュニケーションをいかに取るか。効率よく覚えるものを覚えるか。です。
ちなみに私は最終学科で赤点を取っています。「でめーはもう終わりなんだよ!!荷物まとめて帰れやぁ!!」と言い続けられているところを土下座してもう一度チャンスを下さいと言い続けたのを覚えています。
ハンドル試験と異常時の取り扱いはパスしましたが、仕立て点検でテンパりすぎて肘コックの反位を見逃してその後の点検が出来ず。やはり赤点。この時も罵声を浴びさせられ続けました。この時も土下座してチャンスを貰いましたが、試験車ではない全く違う車両を用意されてやれと・・・
とてつもない時間をかけてしまったがやり切りました。でもその間も「テメー!!出庫時間過ぎてるだろ!!本線支障させてるぞ!!コラぁ!!」と言われ続けてました。
と平成の話をしましたが、今は令和。
蝶よ花よと甘々で教育します。
免許は簡単に取れてしまいます。
あとは自己啓発です。
適当に仕事やって事故起こして処分されるか、無事故で定年を迎えるか。
【保有資格】甲種電気車動力車操縦者免許
私が保有している免許の中で一番大変だったものを紹介します。
「甲種電気車動力車運転免許」合格率98%と言われている免許です。
合格率98%と言え、その過程に入るまでの振るいが多く、受かる人しか受験課程に入れない故の合格率です。
1,鉄道会社に入社する。
中小から大手までたくさんの会社があります。
各社毎年必ず採用をしている訳ではありません。
どんなに小さな会社でも受けたら受かる訳でもありません。
こんな会社でも?と思いましたが、50倍の倍率は普通の様です。
採用時に、一般教養、適性検査、身体検査を行い、鉄道業務に就くための国から指定された条件を満たしているかを確認します。
そこから他の受験者との振るいがかかります。
2,運転士課程への進路がある部署へ配属される。
一般的に、「駅務区」「車両区」が基本。
ただ、車両区でも運転士課程への進路が無い会社もあります。
3,車掌登用試験を受け合格し登用される。
車掌登用は上司の推薦や勤務年数など受験資格は各社ばらばらです。一般的には駅経験1年以上と言われています。
また、ワンマン列車の会社では車掌業務が無いのでこの過程はありません。
4,運転士登用試験を受ける。
指定経験を満たし、上司からの推薦を貰うと運転士登用試験を受けられます。
ここでも学科試験、適性検査、身体検査が行われます。
各駅からも受験者がいるため試験を受けられる権利=課程に入る訳ではない。
5,運転士養成学校へ入所する。(国家試験という道もあり)
大手の場合養成学校を保有しており、そこへ10カ月ほど入ります。
私の時代は寝る間もないほど学科勉強を行い、確実に不健康な生活をしておりました(笑
精神論も多く、ウオーキングや登山なども途中やらされ・・・やらせていただき、精神強化もされます。
学科試験は中間試験、修了試験と2度あり、共に指定された点数を取れないと脱落となります。
各項目80点以上平均90点以上だった覚えがあります。
「車両(起動側)」「車両(制動側)」「鉄道一般」「運心」「作業安全」「保線」「設備」だったと思います。
学科試験を通過すると各乗務所へ異動し指導員の元に就き、半年間ハンドル訓練を行います。
各駅名・停車駅・種別は当たり前とし、各駅間の運転時分秒を記憶、各駅間の最高速度、カーブの半径、信号位置と番号、踏切位置と名前、セクションの場所などすべて知っていて当り前。
計器類が故障した場合でも運転できるように体感速度と距離感を養う事も必須となっています。
車庫訓練では「出庫点検」「非常の場合の処置」「故障処置」の3点を学び、確実に対応出来る事が要求されます。
「出庫点検」は定めらえた時間内にすべての点検が確実に実施される事。また、不具合を確実に見つけられる事も要求されます。
「非常の場合の処置」は主として踏切事故の対応で、非常制動・汽笛・指令連絡などが的確に行うことができるか。列車防護が速やか且つ確実に行うことができるか、運転再開の判断ができ角にできるかが要求されます。
「故障処置」は起こりえる故障全てを的確に判断し、運転再開の対応が速やかに行えるかが要求されます。
そして、実技試験の日
朝から行われます。
指定区間を正しい引継ぎ・正しい執務態度・正しい機器操作・駅間定時・制動時の衝動の有無・停止位置の誤差を審査します。
さらに途中に「中速」「低速」の徐行が行われますが、速度メーターは駅発車時から隠されます。
駅から加速して徐行の指定速度までブレーキをかけ落とし誤差を審査します。
ハンドル試験が終わると今度は車庫での「出庫点検」「非常の場合の処置」「故障処置」の審査をします。
車庫試験は合わせ技で来るので予測と的確な判断能力が必要です。
これらをパスすると「甲種電気車動力車操縦者免許」を取得する権利を得ます。
6,運輸局へ行き免許交付を受けます。

会社を辞めるとこんな感じで所属「無」とされます。
免許分類には
・甲種蒸気機関車運転免許
・甲種電気車運転免許(電気機関車と電車)
・甲種内燃車運転免許(内燃機関車と内燃動車)
・乙種蒸気機関車運転免許
・乙種電気車運転免許
・乙種内燃車運転免許
・新幹線電気車運転免許
・第一種磁気誘導式電気車運転免許
・第二種磁気誘導式電気車運転免許
・第一種磁気誘導式内燃車運転免許
・第二種磁気誘導式内燃車運転免許
・無軌条電車運転免許
とあり、甲種が乙種に勝っているわけではなく、「専用軌道のみを走る甲種」「共用軌道を走る乙種」と別れています。
そこにエンジン(モーター)により区分けされ「蒸気エンジンの蒸気機関車」「電気モーターの電気車」「内燃機関の内燃車」と別れます。
(甲・乙)種(蒸気機関・電気・内燃)車運転免許となります。
それとは別に
「新幹線電気車運転免許」があり、所謂”フル規格新幹線を運転する免許”です。
新幹線電気車運転免許を持っていても普通の鉄道は運転できません。
”フル規格新幹線”の運転免許なので、山形新幹線や秋田新幹線も分岐後は運転できません。
山形新幹線や秋田新幹線は甲種電気車運転免許で運転できます。
第一種磁気誘導式電気車運転免許
第二種磁気誘導式電気車運転免許
第一種磁気誘導式内燃車運転免許
第二種磁気誘導式内燃車運転免許
これらはよくわからないのですが、リニアモータカーの運転免許になると思います。
電気車と内燃車の区分は現在のリニア実験線の車両は内燃機関で動いていると聞きます。それか?
リニアって運転士いるの?と不明たっぷりです。
無軌条電車運転免許
これは古の免許。
トロリーバスの免許です。
昔は都内にもわんさかと走っていたそうですが、今の日本には「立山トンネルトロリーバス」のみとなっています。
あと、不明免許に「限定免許」と言われるものがあります。
「構内限定免許」車両運用さんが車庫内のみを運転するための免許で、社内検定のため他社では意味なしです。
さらに不明な免許でゆりかもめ等で取得者がいる「営業線を運転する限定免許」なるものもあり、所謂新交通の運転免許みたいなものと思われます。
学科時間やハンドル時間は普通の免許より遥かに少ないと言う話です。
もうこんな勉強はご勘弁と言う感じです。
ただ、職責の重さを考えたらこれでも足らない気はします・・・
「甲種電気車動力車運転免許」合格率98%と言われている免許です。
合格率98%と言え、その過程に入るまでの振るいが多く、受かる人しか受験課程に入れない故の合格率です。
1,鉄道会社に入社する。
中小から大手までたくさんの会社があります。
各社毎年必ず採用をしている訳ではありません。
どんなに小さな会社でも受けたら受かる訳でもありません。
こんな会社でも?と思いましたが、50倍の倍率は普通の様です。
採用時に、一般教養、適性検査、身体検査を行い、鉄道業務に就くための国から指定された条件を満たしているかを確認します。
そこから他の受験者との振るいがかかります。
2,運転士課程への進路がある部署へ配属される。
一般的に、「駅務区」「車両区」が基本。
ただ、車両区でも運転士課程への進路が無い会社もあります。
3,車掌登用試験を受け合格し登用される。
車掌登用は上司の推薦や勤務年数など受験資格は各社ばらばらです。一般的には駅経験1年以上と言われています。
また、ワンマン列車の会社では車掌業務が無いのでこの過程はありません。
4,運転士登用試験を受ける。
指定経験を満たし、上司からの推薦を貰うと運転士登用試験を受けられます。
ここでも学科試験、適性検査、身体検査が行われます。
各駅からも受験者がいるため試験を受けられる権利=課程に入る訳ではない。
5,運転士養成学校へ入所する。(国家試験という道もあり)
大手の場合養成学校を保有しており、そこへ10カ月ほど入ります。
私の時代は寝る間もないほど学科勉強を行い、確実に不健康な生活をしておりました(笑
精神論も多く、ウオーキングや登山なども途中やらされ・・・やらせていただき、精神強化もされます。
学科試験は中間試験、修了試験と2度あり、共に指定された点数を取れないと脱落となります。
各項目80点以上平均90点以上だった覚えがあります。
「車両(起動側)」「車両(制動側)」「鉄道一般」「運心」「作業安全」「保線」「設備」だったと思います。
学科試験を通過すると各乗務所へ異動し指導員の元に就き、半年間ハンドル訓練を行います。
各駅名・停車駅・種別は当たり前とし、各駅間の運転時分秒を記憶、各駅間の最高速度、カーブの半径、信号位置と番号、踏切位置と名前、セクションの場所などすべて知っていて当り前。
計器類が故障した場合でも運転できるように体感速度と距離感を養う事も必須となっています。
車庫訓練では「出庫点検」「非常の場合の処置」「故障処置」の3点を学び、確実に対応出来る事が要求されます。
「出庫点検」は定めらえた時間内にすべての点検が確実に実施される事。また、不具合を確実に見つけられる事も要求されます。
「非常の場合の処置」は主として踏切事故の対応で、非常制動・汽笛・指令連絡などが的確に行うことができるか。列車防護が速やか且つ確実に行うことができるか、運転再開の判断ができ角にできるかが要求されます。
「故障処置」は起こりえる故障全てを的確に判断し、運転再開の対応が速やかに行えるかが要求されます。
そして、実技試験の日
朝から行われます。
指定区間を正しい引継ぎ・正しい執務態度・正しい機器操作・駅間定時・制動時の衝動の有無・停止位置の誤差を審査します。
さらに途中に「中速」「低速」の徐行が行われますが、速度メーターは駅発車時から隠されます。
駅から加速して徐行の指定速度までブレーキをかけ落とし誤差を審査します。
ハンドル試験が終わると今度は車庫での「出庫点検」「非常の場合の処置」「故障処置」の審査をします。
車庫試験は合わせ技で来るので予測と的確な判断能力が必要です。
これらをパスすると「甲種電気車動力車操縦者免許」を取得する権利を得ます。
6,運輸局へ行き免許交付を受けます。

会社を辞めるとこんな感じで所属「無」とされます。
免許分類には
・甲種蒸気機関車運転免許
・甲種電気車運転免許(電気機関車と電車)
・甲種内燃車運転免許(内燃機関車と内燃動車)
・乙種蒸気機関車運転免許
・乙種電気車運転免許
・乙種内燃車運転免許
・新幹線電気車運転免許
・第一種磁気誘導式電気車運転免許
・第二種磁気誘導式電気車運転免許
・第一種磁気誘導式内燃車運転免許
・第二種磁気誘導式内燃車運転免許
・無軌条電車運転免許
とあり、甲種が乙種に勝っているわけではなく、「専用軌道のみを走る甲種」「共用軌道を走る乙種」と別れています。
そこにエンジン(モーター)により区分けされ「蒸気エンジンの蒸気機関車」「電気モーターの電気車」「内燃機関の内燃車」と別れます。
(甲・乙)種(蒸気機関・電気・内燃)車運転免許となります。
それとは別に
「新幹線電気車運転免許」があり、所謂”フル規格新幹線を運転する免許”です。
新幹線電気車運転免許を持っていても普通の鉄道は運転できません。
”フル規格新幹線”の運転免許なので、山形新幹線や秋田新幹線も分岐後は運転できません。
山形新幹線や秋田新幹線は甲種電気車運転免許で運転できます。
第一種磁気誘導式電気車運転免許
第二種磁気誘導式電気車運転免許
第一種磁気誘導式内燃車運転免許
第二種磁気誘導式内燃車運転免許
これらはよくわからないのですが、リニアモータカーの運転免許になると思います。
電気車と内燃車の区分は現在のリニア実験線の車両は内燃機関で動いていると聞きます。それか?
リニアって運転士いるの?と不明たっぷりです。
無軌条電車運転免許
これは古の免許。
トロリーバスの免許です。
昔は都内にもわんさかと走っていたそうですが、今の日本には「立山トンネルトロリーバス」のみとなっています。
あと、不明免許に「限定免許」と言われるものがあります。
「構内限定免許」車両運用さんが車庫内のみを運転するための免許で、社内検定のため他社では意味なしです。
さらに不明な免許でゆりかもめ等で取得者がいる「営業線を運転する限定免許」なるものもあり、所謂新交通の運転免許みたいなものと思われます。
学科時間やハンドル時間は普通の免許より遥かに少ないと言う話です。
もうこんな勉強はご勘弁と言う感じです。
ただ、職責の重さを考えたらこれでも足らない気はします・・・





